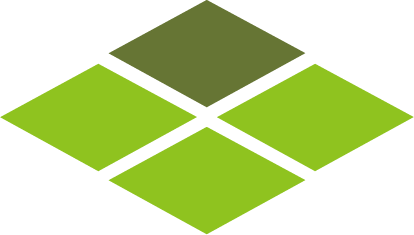 神社紹介
神社紹介 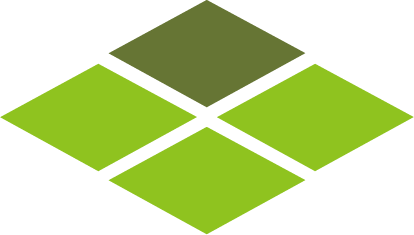
武生神社
- 神社名 :武生神社 (たきゅうじんじゃ)
- 宮司名 :荷見不可止 (はすみふかし)
- 連絡先 :電話 0294-87-0789
- 鎮座地 :茨城県常陸太田市下高倉町2268
- アクセス:JR水郡線常陸太田駅から茨城交通バス
- 下高倉行45分 武生山入口下車 徒歩30分
- 車の場合、常陸太田駅より24km 約30分
- 駐車場 :約15台分有り
【御祭神】
大戸道尊 (おおとのじのみこと)
【御神徳】
武運長久(勝負事)、厄除、交通安全、家内安全等
【御由緒】
当社の北西に山あり、これを本宮(もとみや)と云う。神武天皇のころ「大戸道尊」がこの山頂に降臨され、大宝元年(701年)に役小角が武生山上に遷祀、社殿が創建されたのが大同元年(806年)3月1日と伝えられる。
征夷大将軍坂上田村麻呂が蝦夷征伐の際、武運長久を祈願、神恩を感謝して本殿を興造して「やぶさめ」の神事を奉納、この儀式は長く伝えられた。
永正7年(1510年)滝生山明王寺が建立され、両部神道の道場となり、後に僧侶が奉仕することになったが、徳川光圀公の命に依り修験道の昔に復し、武生山大権現と称し大王院(又は大音院)が別当職として明治の神仏分離布告まで続いた。
【祭礼・行事/期日】
元旦祭 1月1日
例祭 旧3月1日
献穀祭 11月23日
八朔祭 9月15日(三年に一度神幸祭あり)
【境内社】
稲荷神社 (いなりじんじゃ)
鎮霊社 (ちんれいしゃ) 明治以降第二次世界大戦まで武生神社の氏子の戦死者の霊を祀る。9月23日慰霊祭
【御神紋、社紋】
五本骨扇に日の丸
【文化財、ご神木等の特色】
〈本殿〉
常陸太田市指定有形文化財 明治6年(1786年)の再建で、現在は美しい彩色を施されている。
〈太郎杉〉
常陸太田市指定天然記念物 樹齢約800年

